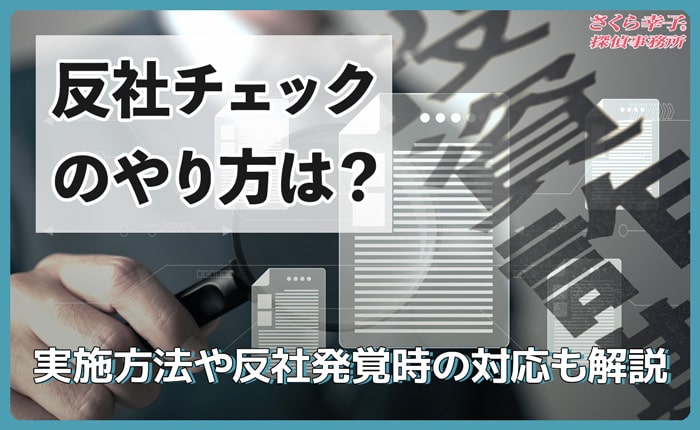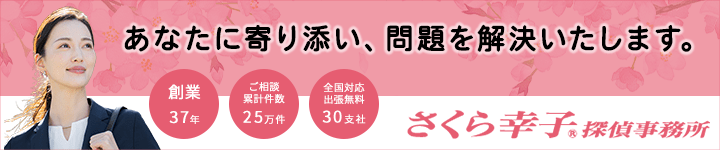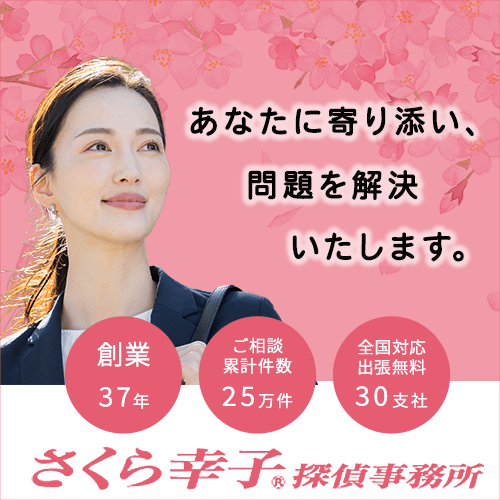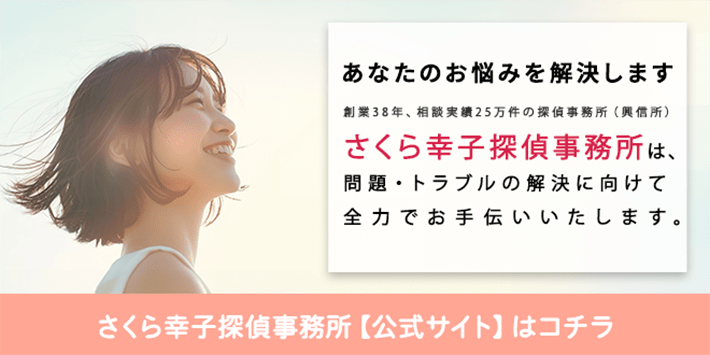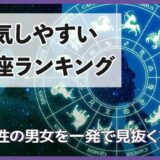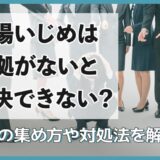反社チェックとは企業や従業員など、対象が反社会的勢力と関わりがないのかを把握する取り組みです。企業にとって反社チェックは、自社が事業を進めるうえで欠かせません。そのため、適切な方法でチェックを実施しましょう。
この記事では、反社チェックのやり方や反社会的勢力との関係が発覚した場合の対応などを解説します。
- 反社チェックが必要な理由
- 反社チェックの対象
- 反社チェックの実施方法
反社チェックの対象は3つ
企業が実施する反社チェックの対象は主に次の3つです。
- 取引先企業
- 自社の従業員や役職者
- 株主
それぞれの対象に対してのチェックについて解説します。
取引先企業

企業が反社と関わるリスクを避けるために、取引先企業に対する実態の調査は欠かせません。特に、契約書を締結する前や取引開始前に、相手企業の背景を確認することが重要です。反社チェックが完了する前に契約を交わしてしまうと、万が一、チェックにひっかかった場合に自社のリスクになってしまいます。そのため、反社会的勢力と関りがあった場合は契約を破棄する旨を示しておきましょう。
取引先のチェックは新規だけでなく、すでに取引している企業に対しても実施が必要です。契約当初は実態に問題がなくとも、状況が変化したことで、反社チェックに引っかかる可能性があります。
自社の従業員や役職者
自社の従業員や役職者も反社チェックの対象です。例えば、新たに採用する従業員が反社会的勢力と関わりがないのかをチェックします。対象となるのは正社員に限りません。アルバイトで採用した学生であってチェックが必要です。学生といえども、SNSを通じて反社会的な存在とつながりを持っている可能性があるためです。
同様に、新たに自社の役職に就く従業員に対してもチェックを実施しましょう。役職者が反社会的な存在と関わりがあることが発覚すると、自社の社会的信頼が大きく失墜してしまいます。
株主
株主への反社チェックも欠かせません。株主は企業にとって会社の所有者ともいえ、経営に参画する権利を持つ重要な存在です。そのため、株主が反社会的な存在と関わりがあれば、経営に大きな影響を及ぼしかねません。
企業の株主は個人だけではありません。法人が株主の可能性もあります。法人が株主であれば、代表者だけでなく役員、株主、顧問弁護士、税理士までも調査が必要です。
レベル別の反社チェックのやり方
反社チェックのやり方は次のとおりレベルごとに異なります。
- 一般的な反社チェック:公知情報からの情報収集
- 危険を伴う反社チェック:警察や全国暴力追放運動推進センターへの問い合わせ
- 精度の高い反社チェック:調査期間や興信所への調査依頼
公知情報からの情報収集

一般的な反社チェックの方法は、公知情報からの情報収集です。企業の取引先や従業員、役職者については、インターネットや報道機関、業界団体などからの情報を集めることができます。これにより、反社会的勢力との関係が疑われる事例を事前に発見可能です。
具体的には、取引先企業の登記情報、代表者名、過去の事件や裁判歴などを調査しましょう。また、警察や暴力団排除条例に基づく情報提供サービスを活用することも、効率的なチェック方法です。この方法は比較的簡便でコストも抑えられるため、初期の調査段階において有効です。
警察や全国暴力追放運動推進センターへの問い合わせ
公知情報に基づく反社チェックによって、取引先に関する危険度が高い情報が収集された場合、取引先が反社会的勢力の恐れがあります。
取引先の危険性が高いのであれば、取引先の氏名や生年月日、可能であれば住所などの情報を確認したうえで、警察や全国暴力追放運動推進センターに相談することが重要です。
警察や全国暴力追放運動推進センターは反社会的勢力の情報を管理しています。そのため、企業がそのリスクを負わないために、取引先が暴力団関係者であるかどうかを確認するための信頼性の高い情報源となります。
警察や暴力追放運動推進センターに対して提供する情報は、可能な限り詳細に準備し、迅速に連絡を取りましょう。また、情報提供の際には、プライバシーや機密情報を取り扱う際の慎重さを保ちつつ、必要なデータを提供しましょう。
調査期間や興信所への調査依頼
インターネットや報道機関などの情報だけでは十分な情報が得られなかったのであれば、調査期間や興信所へ調査依頼をしましょう。興信所や調査会社は専門的な知識とネットワークを持ち、より深い調査が可能です。調査期間や調査対象を明確に設定し、専門機関に依頼することで、反社との関わりを効率的に洗い出せるでしょう。
調査を依頼する際には、費用対効果を考慮し、必要な情報に対して適切な調査方法を選択することが重要です。また、調査依頼を行う際には、機密情報の取り扱いにも十分な配慮が求められます。
反社チェックを実施する目的
反社チェックを実施する目的は主に次のとおりです。
- 反社に資金提供しないため
- コンプライアンスを遵守するため
それぞれの目的について解説します。
反社に資金提供しないため

企業が反社と取引を行った場合、企業は資金提供を行ったことになり、その資金が反社活動に流れる可能性が生じます。
反社活動に資金が使われている場合、企業は社会的責任を問われかねません。例えば、反社との取引が判明したことで、金融機関や取引先からの信頼を失う可能性があり、最終的には事業の継続に支障をきたすこともあるでしょう。さらに、暴力団排除条例違反のように法的な制裁を受けるリスクも高くなります。
そのため、企業は取引先や従業員、役職者のバックグラウンドを徹底的に確認し、反社との関わりを断つことが求められます。反社チェックを行うことで、企業が自らの資金やリソースを反社活動に流用させることを防ぎ、健全な企業運営を守ることができるのです。
コンプライアンスを遵守するため
企業が法令や業界の規範を遵守することは、社会的な責任を果たすために欠かせません。特に、反社会的勢力との関わりを避けるためのコンプライアンス強化は、企業経営において重要な要素です。先述のとおり、反社との取引が発覚した場合、企業は法的な制裁や行政からの指導を受けるだけでなく、社会的な信用を失うことになります。この信用の失墜は、顧客や取引先との関係に大きな影響を与え、最終的には事業運営に致命的な打撃を与える可能性もあります。
そのため、企業がコンプライアンスを遵守するためには、反社チェックを継続的に実施することが不可欠です。従業員や取引先が反社に関与していないかを確認することで、企業の社会的責任を全うし、法令を守ることができるのです。
業種別の反社会的勢力排除ルール
反社会的勢力との関わりを禁止する条例として、暴力団排除条例が全国で制定されています。
暴力団排除条例以外にも次のとおり、業種ごとに反社会的勢力との関係を排除するルールが定められています。
| 業種 | ルール |
|---|---|
| 不動産業界 | ・宅建業法による規制・不動産関係団体と国土交通省による、反社会的勢力排除のためのモデル契約書の策定 |
| 生命保険・損害保険業界 | ・生命保険協会による生命保険業界における反社会的勢力への対応指針の策定・日本損害保険協会による損害保険業界における反社会的勢力への対応に関する指針 |
| 証券業界 | ・日本証券業協会による反社会的勢力との関係遮断に関する規則の策定・金融商品取引法による規制 |
| 銀行・金融業界 | ・金融商品取引法、銀行法、貸金業法による規制 |
| 中小企業 | ・中小企業団体による企業指針の普及促進 |
反社チェックをしないリスク
反社チェックをしないで事業を進めていると次のようなリスクにつながりかねません。
- 社会的信用がなくなり倒産のリスクが高まる
- 自社や従業員が犯罪に巻き込まれかねない
それぞれのリスクを詳しく解説します。
社会的信用がなくなり倒産のリスクが高まる

反社チェックを怠ることで、企業は意図せずとも反社会的な勢力と関わってしまう恐れがあります。先述のとおり社会的信用を失うリスクにつながってしまうでしょう。
社会的信用は、企業が安定的に事業を運営していくための基盤です。信用を失うと、顧客や取引先との契約が継続できなくなる可能性が高まり、最終的には事業の継続が困難になります。
特に、近年では企業が反社と関わっていることが発覚すると、メディアでの報道やSNSでの拡散により、瞬時に企業の信用が失われかねません。
自社や従業員が犯罪に巻き込まれかねない
反社チェック未実施のリスクのひとつが、自社や従業員が犯罪に巻き込まれる可能性があるという点です。
反社会的勢力は、暴力団や詐欺集団など、違法行為を行う団体であるため、その活動に関与することは重大な法的リスクを引き起こします。企業が反社との取引を行った場合、企業自体が犯罪行為に加担しているとみなされ、刑事責任を問われる可能性もあるでしょう。
また、従業員が反社との関係を持つ場合、企業全体の信頼性に悪影響を与えるだけでなく、従業員自身も法的責任を問われることになります。このようなリスクを避けるためには、従業員や取引先に対して反社チェックを行い、早期に問題を発見することが不可欠です。企業が反社との関わりを未然に防ぐことで、従業員や企業自体が法的な問題に巻き込まれることを防ぎ、健全な運営が可能です。
反社チェックを実施するタイミング
反社チェックを実施するタイミングは主に次のとおりです。
- 新規取引開始の際
- 従業員入社や役員就任の前
- 新規上場の際
適切なタイミングでの反社チェック実施によって、自社が被るリスクを軽減できます。
新規取引開始の際

先述のとおり、新規の取引開始時は反社チェックが欠かせません。
取引先が反社会的勢力と関わりがあると、企業は信頼を失い、法的なリスクを抱えることになります。そのため、取引開始前に、取引先の背景を調査し、反社との関係がないかを確認することが大切です。これにより、企業は反社からの資金提供を受けることなく、健全な取引につながります。
取引先の反社チェックは、公開されている情報を基に行うことが一般的です。企業名や代表者名、事業内容、過去の裁判記録などの情報を調べることで、相手企業の信用度や反社との関係を把握できます。新規取引開始時にチェックを行うことで、後々のトラブルを未然に防止可能です。
なお、取引先への反社チェックは新規契約の締結時だけでなく、新たに役員が就任したタイミングに実施するのも大切です。役員が入れ替わると体制が変わるため、反社会的勢力と関わりを持つ恐れもあるためです。
従業員入社や役員就任の前
従業員や役員の採用前にも反社チェックを行うことは重要です。採用時には、過去の職歴や交友関係など、従業員が反社と関わっていないかを確認するために、事前に十分な調査を行うことが求められます。
特に、経営陣や役職者が反社会的勢力との関係を持っていると、企業全体の信用に大きな影響を与える可能性があります。役員や重要なポストに就任する人物については、より慎重な調査が必要です。役員就任前にも、個人のバックグラウンドや資産状況を確認することで、リスクを最小限に抑えることができます。
新規上場の際
企業が新規上場を行う際にも、反社チェックは欠かせません。上場企業として社会的な責任が増すため、上場前に反社との関係を清算しておくことが求められます。特に、大株主や主要取引先、経営陣に反社が関与していないかを確認することが必要です。
実際、東京証券取引所へ上場するには、該当企業は申請書の添付書類として「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」の提出が必要です。(※1)
新規上場に向けて、企業の健全性を証明するためには、反社会的な勢力とつながりがないのかを徹底的に行い、反社会的勢力との関わりがないことを証明する必要があります。あわせて、反社会的勢力との関わりを避けるための体制整備も求められます。
反社の可能性が疑われる場合の対応
取引先や自社の従業員、役員が反社会的勢力と関わっていることが判明した場合、次のような対応を取りましょう。
- 上司や経営陣に相談する
- 反社の疑いは相手に伝えない
- 弁護士や警察に相談する
上司や経営陣に相談する

取引先や自社の従業員が反社の疑いがある場合、まずは上司や経営陣に相談することが大切です。企業内部で早期に問題を共有することで、適切な対応策を講じることができます。反社との関わりが疑われる場合、単独で判断せずに、関係者と情報を共有し、慎重に行動を起こしましょう。
特に、反社との取引を開始してしまった場合、上司や経営陣と連携して、速やかに取引を中止するための手続きを進めるのがポイントです。また、反社との関係を断ち切るためには、経営陣が中心となって、社内外の関係者と連携して行動することが求められます。
反社の疑いは相手に伝えない
反社との関わりが疑われる場合、相手に伝えることは避けましょう。反社に関与している企業や個人に対して、その疑念を公にすることは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
疑いがある場合でも、相手に対して公に反社との関わりを指摘することは、相手に対して不当な契約解除を引き起こし、訴訟リスクにつながりかねません。そのため、まずは内部で十分に調査を行い、問題が確認された時点で適切な対応を取るようにしましょう。
不当契約解除のリスクを避けるためには、あらかじめ反社チェックの結果に応じて、契約する旨を伝えておきましょう。
弁護士や警察に相談する
取引先や自社の従業員が反社との関わりが疑われるのであれば、弁護士や警察への相談も検討しましょう。反社との取引を行っていた場合や、企業内で反社と関わっている可能性がある従業員がいる場合、法律的なアドバイスを受けることで、今後の対応方針を明確にすることができます。
また、警察に相談すれば、反社に関する正式な情報を得ることが可能です。法的なアプローチを取ることで、企業が適切に反社との関わりを断ち切り、法的なリスクを回避することができます。
反社チェックを実施して自社のリスクを最小化しよう
反社チェックは取引先企業や自社の従業員や役職者、株主を対象に実施するのが一般的です。それぞれ新たな取引開始時や新規採用、役員就任などのタイミングに実施が理想的です。
反社チェックを放置していると自社の信頼が低下するだけでなく、従業員に危害が加わる恐れすらあります。そのため、新聞やインターネットなど公知情報を活用して自社で反社会的勢力との関係を調査しましょう。自社だけでの調査では十分な結果が得られない、自社に危険が及ぶ可能性があるといった場合、専門家である探偵への調査が有効です。探偵であれば、一般企業では把握できないような情報を調査できます。